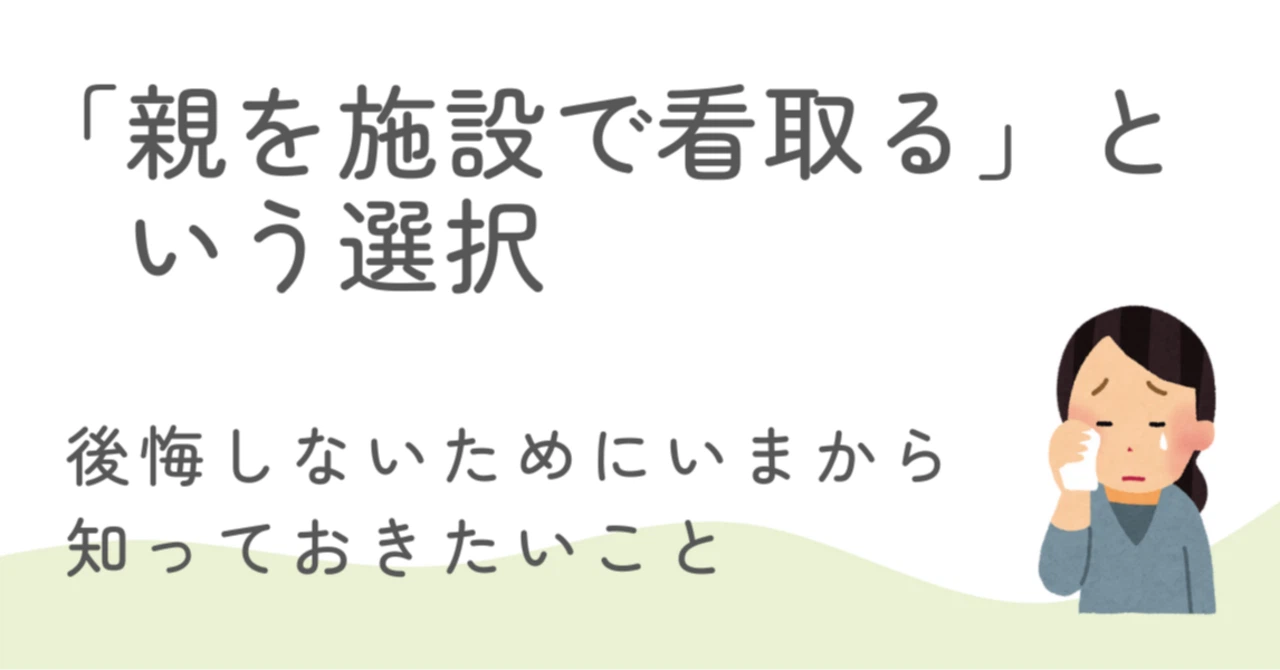
はじめに

「そろそろうちの親も老人ホームを考えないといけないけど、最期まで面倒を見てもらえるのかな?」
そんなふうに、老人ホームへの入所を考え始めたときに
「最期まで施設でみてもらえるの?」
「いよいよ悪くなったら、どうやってお世話してくれるの?」
と、不安や疑問を抱く方は多いと思います。
でも、大丈夫。
今は多くの施設で「看取りケア」という
その方の最期まで寄り添うケアが行われるようになってきています。
今回は、「老人ホームでの看取り」について
特別養護老人ホームで100人以上のお看取りを経験した元・相談員の私がわかりやすく解説します。
この記事を読めば、
「施設で最期を迎えるって、こんな感じなのか」とイメージを持っていただけますよ。
看取りケアってなに?

「看取りケア」とは、医療による回復が難しくなった方に対しておこなわれる、
その方らしい穏やかな最期を迎えられるように支える支援のことです。
病気を治すための医療とは違い、
身体的・精神的な苦痛をできるだけ和らげて、ご本人が望む形で最期の時間を過ごせるようにサポートします。
ご高齢になり、いわゆる「老衰」と呼ばれる時期になると、点滴や胃ろうなどで命をつなぐ選択を迫られることもあります。
このような選択をせまられたとき
「最期まで管につながれて生きるのが、本当に本人が希望する最期なのか⋯⋯」
と悩まれるご家族は少なくありません。
こうした背景から、「医療的行為だけに頼らず、最期まで自分らしさを大切にしたケアを受けたい」というニーズが高まり、老人ホームでも看取りケアが広く導入されるようになってきました。
どういう状態が看取りなの?
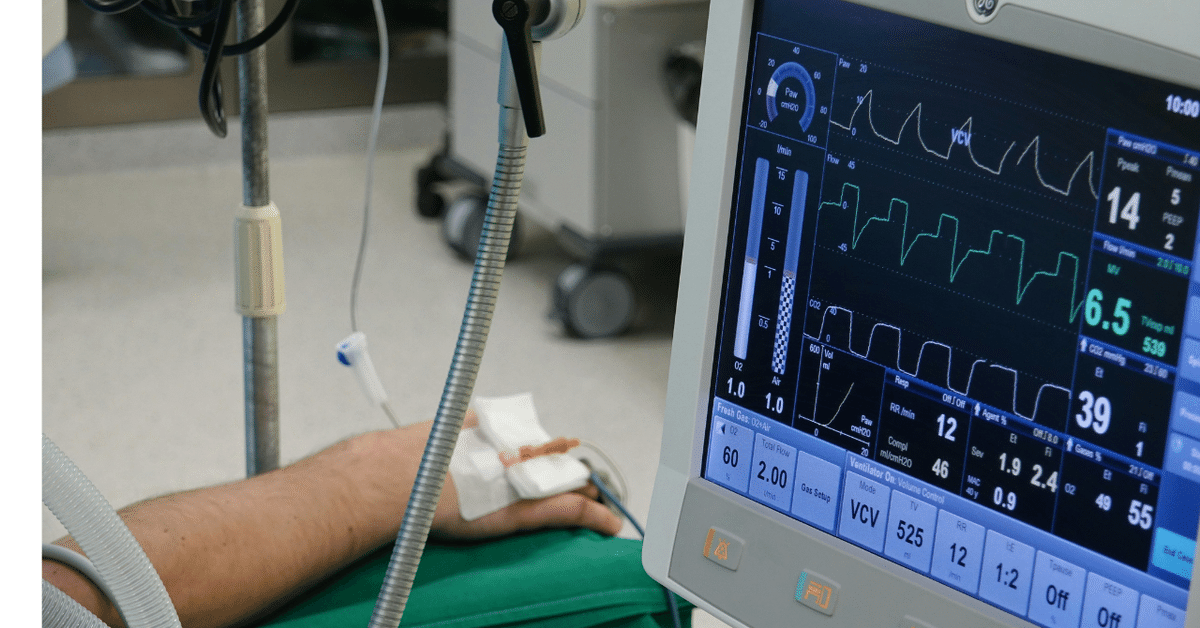
医師が看取り期の判断をするのは、以下のような状態になった場合です。
・食事や水分の摂取量が著しく低下している
・意識が低下し反応が鈍くなっている
・がんや心不全などの疾患が末期である
・血圧・脈拍・呼吸数などに異常が続いている
こうした兆候が見られると、ご家族に連絡が入り看取りケアを希望するかどうかを確認する流れになります。
ここで、よくある誤解についても触れておきたいのですが
看取りケアとは「回復の見込みがあるのに何もしない」ということではありません。
看取りケアの対象になるのは
あくまで「老衰」や「治療が困難な病状の進行」に限られます。
風邪や骨折など、治療すれば回復が見込めるケースは、看取りケアの対象とはならないということです。
延命治療をしないのはかわいそう?

「看取りケアって、なんだかかわいそう⋯⋯。病院に行けばもっと長生きできるんじゃないの?」
ここまで読んでくださった方のなかには、そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。
「このまま看取りにしてしまったら見殺しにしているみたいでかわいそうじゃないでしょうか…」
と看取りを施設に頼むべきか悩んで相談して来られるご家族もたくさんいらっしゃいました。
「1日でも長く生きることが幸せ」と考える方もいらっしゃいますし、価値観は人それぞれ、死生観に正解はありません。
しかし
「病院で延命治療をうけることもできます」
とご提案すると
「本人に聞いてみないと決められない。でも、もう意思を確認できる状態じゃない⋯⋯」
と悩まれるご家族が少なくありませんでした。
だからこそ「前もって聞いておけばよかった」と後悔しないためにも、家族が元気なうちに「最期の過ごし方」について話し合う時間を持っておくことが大切なのです。
少し話がそれますが、私の父は「進行性核上麻痺」という病気を持っています。
この病気は、食事や水分を飲み込む力が少しずつ低下していくという疾患です。
父が食事中にむせるようになってきたので
「最期、どうしたいかを今のうちに聞いておかないと」
と思った私は、つい前置きもなく
「おとうさん、もし食べられなくなったら胃ろうにしたい?」
と聞いてしまいました。
すると父は、すごく落ち込んでしまったんです⋯⋯。
「最期の希望を確認するなら、早ければ早いほどいい。病気になってからでは遅い」
と痛感した出来事でした。
医療ケアは「苦痛を和らげるため」に行う

「看取りケアって、もう医療的なことは一切はしないの?」と聞かれることもありますが、そんなことはありません。
延命治療(命を無理に長らえさせる医療)は行いませんが、痛みや苦しみを和らげる下記のような医療ケアは積極的に行います。
- 痛みがあるときの痛み止めの使用
- 息苦しさがあるときの酸素吸入
看取りケアの「最期の瞬間」と家族の対応について
看取り期に入ると、徐々に食事や水分が摂れなくなり、眠る時間が増えていきます。
目を開けていてもぼんやりしていて、会話が難しくなることも少なくありません。
この段階は「意識があるうちに会える最後のチャンス」
可能な範囲での面会に行かれるとよいでしょう。
あとになって
「会話ができるうちにもっと話しておけばよかった……」
と後悔しないよう、できるだけ早めに会いに行くことがおすすめです。
やがて臨死期(死が差し迫った状態)を迎えると、血圧や脈拍が低下し、尿が出なくなり、呼吸も浅くなるなど変化していきます。
この状態になると、死は数時間以内とされ、いよいよお別れの時が近づいているサインです。
ご家族には施設から「お別れの準備を」と連絡が入るので
臨終に立ち会いたい場合は、すぐに施設へ向かいましょう。
施設でのご臨終後の流れ
ご本人が施設で亡くなられた場合、まず医師による死亡確認が行われます。
宗教法人が運営している場合など、その場でお経をあげてもらえることもありますが、おおくの場合はご家族に葬儀社の手配を行ってもらいます。
「葬儀屋なんてどうやって探せば…」
と不安な方も、事前に登録している互助会や決まった葬儀社があればそちらへ連絡を。
ネットで調べて初めて連絡したところでも、葬儀社のスタッフが親切に案内してくれますよ。
ご遺体の搬送とその後
霊柩車が到着すると、職員が黙祷や合掌でお見送りし、ご遺体は葬儀会館または火葬場へと向かいます。
「最後に自宅に連れて帰ってあげたい」
というご家族の思いから、一度自宅を経由するケースもあれば、宗教的・経済的な事情で直接火葬場へ行かれるご家庭もあります。
現場で感じた「看取り」のリアル あなご寿司が教えてくれたこと

私はこれまで、15年間の施設勤務で100人以上の方の旅立ちに立ち会わせていただきました。
その中でも、今も心に残っているのが看取りの最後に「あなごのお寿司を食べたい」とおっしゃった女性の利用者さんとのエピソードです。
その方は、看取りケアが始まってから1週間ほど、食事も水分も摂らずに静かに過ごされていました。
もう食欲はないのだろうと思っていたある日、週末に息子さんが面会に来られたときのこと。
その方は息子さんに
「あなごのお寿司が食べたい」と、ぽつりと一言おっしゃったのです。
驚いた息子さんは「でも、食べさせても大丈夫なんですか?」と不安そう。
けれどその目は「なんとか食べさせてあげたい」という強い気持ちでいっぱいでした。
「ご本人とご家族が望まれるなら、できる限り応えよう」
私たち職員もすぐに動き出しました。
お寿司が喉に詰まる事態に備えて吸引機を準備し、酸素ボンベも手配。
息子さんは、以前はおかあさんを連れてよく行ったという回転寿司店へ、あなご寿司を買いに走りました。
「ほら、おふくろ。寿司だよ」
息子さんがパックを開けて見せると、ここ数日反応が薄かったその方が、嬉しそうに
「おいしそうだねえ」
と笑顔を見せてくださいました。
そして、小枝のように細くなった指でお寿司をつまみ、口元へ。
ムセることもなく、ひと口、ふた口としっかりと味わい
「おいしい」
と穏やかに微笑まれたのです。
息子さんは「元気そうで安心したよ」と涙ぐみ、私たち職員も胸がいっぱいになりました。
その日の施設は、あなご寿司の話題でいっぱいでした
そしてその夜、その方は静かに息を引き取られました。
最期のときはご自宅ではなく施設のベッドでしたが、きっと「家族と行った回転寿司の思い出」を心に浮かべながら、あたたかな気持ちで旅立たれたのではないかと思います。
まとめ

看取りケアは、「最期のときをどう迎えるか」に不安を感じている方にとって、大きな選択肢のひとつです。
人の最期に「こうすべき」という正解はありません。
でも、事前に知っておくことで
「あのとき、こうしていれば…」という後悔を減らすことはできるかもしれません。
「もっと早く知っていればよかった」
大事な人の最期を迎えるとき、そう思わなくて済むように、今のうちから、少しずつでも準備を始めてみてはいかがでしょうか。